
信託制度を利用すると、何がどうなるのか?
まずその理屈を、簡単に理解することにしよう。信託を活用すると次のような
ことができるようになります。
税法上、信託受益権を有する者は、信託資産の所有者とされます。
残余財産の評価は、信託財産の時価によります。
信託終了に際しては、終了時の受益者から信託の残余財産の取得者に対して、
贈与による資産移転があったものみなします。
不動産の管理代行
生前贈与の制度を使って一旦、息子に贈与した例えば不動産を、その息子に
変わって親が管理できます。知らせないで行うことも可能です。実際には、
次のような形態が考えられます。
(1)高齢の親の財産を、子が管理代行できる。
(2)遺産を引き継いだ子の財産を、その親が管理代行ができる
(3)子に贈与したことを伝えず贈与できる
※信託は贈与税が掛らないようにできる。
贈与税は「受益権」に掛るから、その子に受益権を与えなければ
贈与税は掛らない。
(1) 自分が亡くなった後、相続人の相続まで(30年先まで)指定すること
(2) 遺言書が書き換えできないように確定させること
(3) 遺産を確実に相続させること
1.信託を活用する対策とは、
後継者でない子供に承継する予定の株式を信託して、受益権を後継者で
ない子供に相続する方法です。
2.権利関係
信託された株式については、受託者が株主となり、株主としての権利を
行使することになります。後継者又は後継者が支配できる法人等を受託者
にしておけば、株主としての権利は全て後継者である長男の意のままに
なるので、議決権等を制限する必要はありません。
注: 種類株式で議決権の制限など、株式の内容変更には全株主の同意
が必要です。一方、信託の場合には、委託者(推定の被相続人)と
受託者の同意のみが必要です(他の株主の同意は不要)。
普通株式を無議決権株式する手法は、株主に本来認められている
権利として制限できない権利が幾つかあります。一方、信託は、
受託者=株主となり、信託の目的に従って、受託者が株主の権利を
行使します。なお後継者でない子供の受益権は株主権ではないので
株主として権利行使はできません。
この場合、後継者でない子供は信託受益権を相続により取得する
ので信託受益権の相続評価額は信託財産の価額と同額になります。
つまり、後継者でない子供は株式相続と同様の評価額で信託受益権
を評価し相続税が掛ります。後継者でない子供は信託契約の定めに
従って微々たる配当受取権はありますが、議決権等の株主権の行使
は不可です。受益権を取得した後継者でない子供には不利です。
このバランス上の問題は、事前の対応が必要ですが結果的に株式
は売却されることになり通常、会社を承継する後継者、または会社
自体で買い取ります。
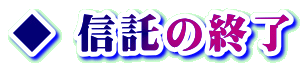
タックスプランニングとして、親が、長男太郎を、委託者兼受益者とし、
太郎丸株式会社を受託者として、例えば、同族会社の株式(株)を信託する
契約をする場合の戦略を考えて見ましょう。なお、親の死亡で、信託が終了
する場合は、遺贈として相続税が掛ります。
1.信託契約書に、信託終了で残余財産の帰属が、太郎としてあったときは、
イ)信託終了による信託残余財産(株)は太郎が取得します。
ロ)信託終了前の受益者は太郎で、太郎は、受益者として信託財産(株)
の権利を持っていました。
ハ)ゆえに、太郎は信託契約の終了に際して、信託財産(株)は贈与財産
から除外されます。贈与税は対象外です。
2.上記1の帰属が、孫一なら、
イ)信託終了で孫一が残余財産(株)を取得します。
ロ)信託終了前の受益者は太郎。
そのため、信託終了に伴い、孫一が残余財産(株)を太郎から贈与さ
れたと考えるのです。孫一に贈与税が掛ります。
注: 委託者と受託者が、株100%保有のグループ法人間では、寄付金に
対応する受贈益は益金(課税所得)になりません。繰延べされます。

